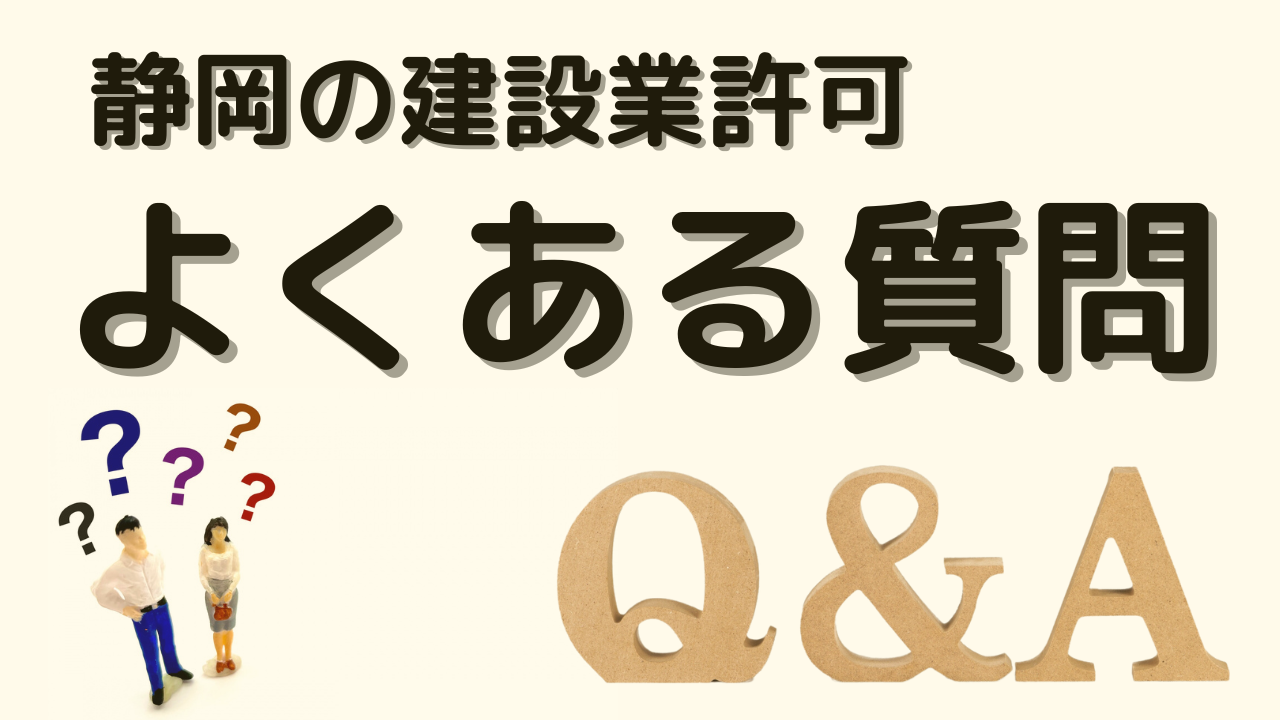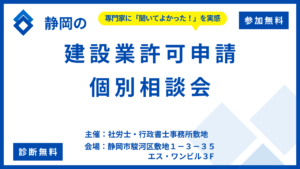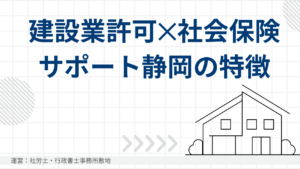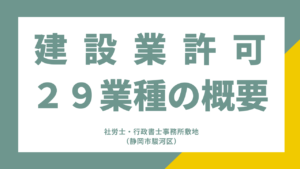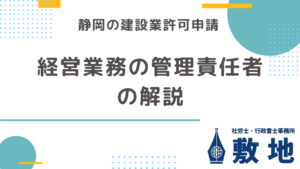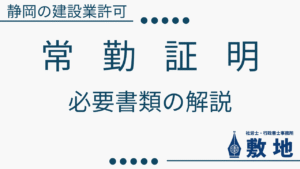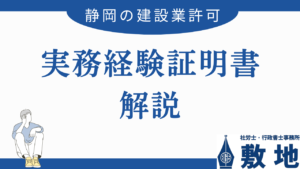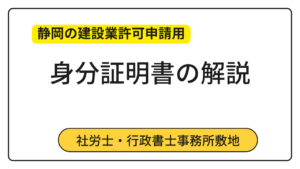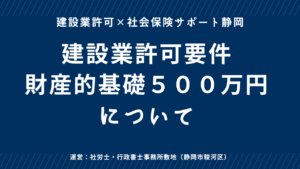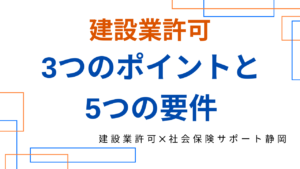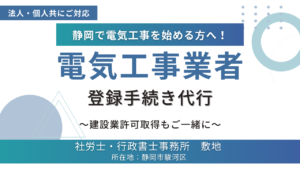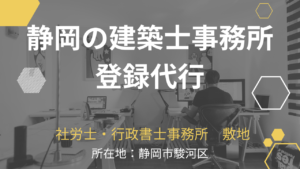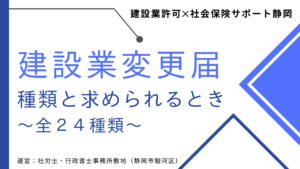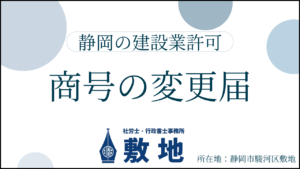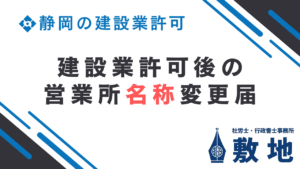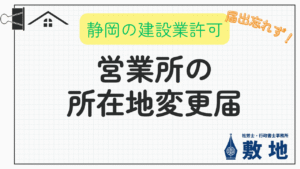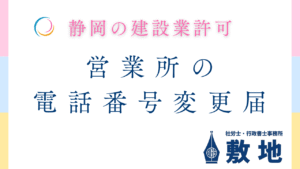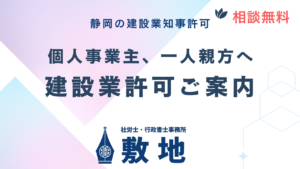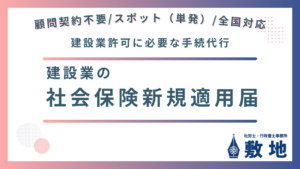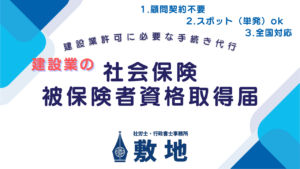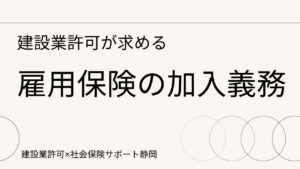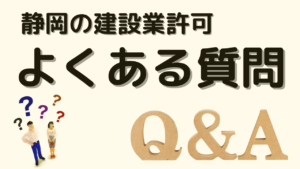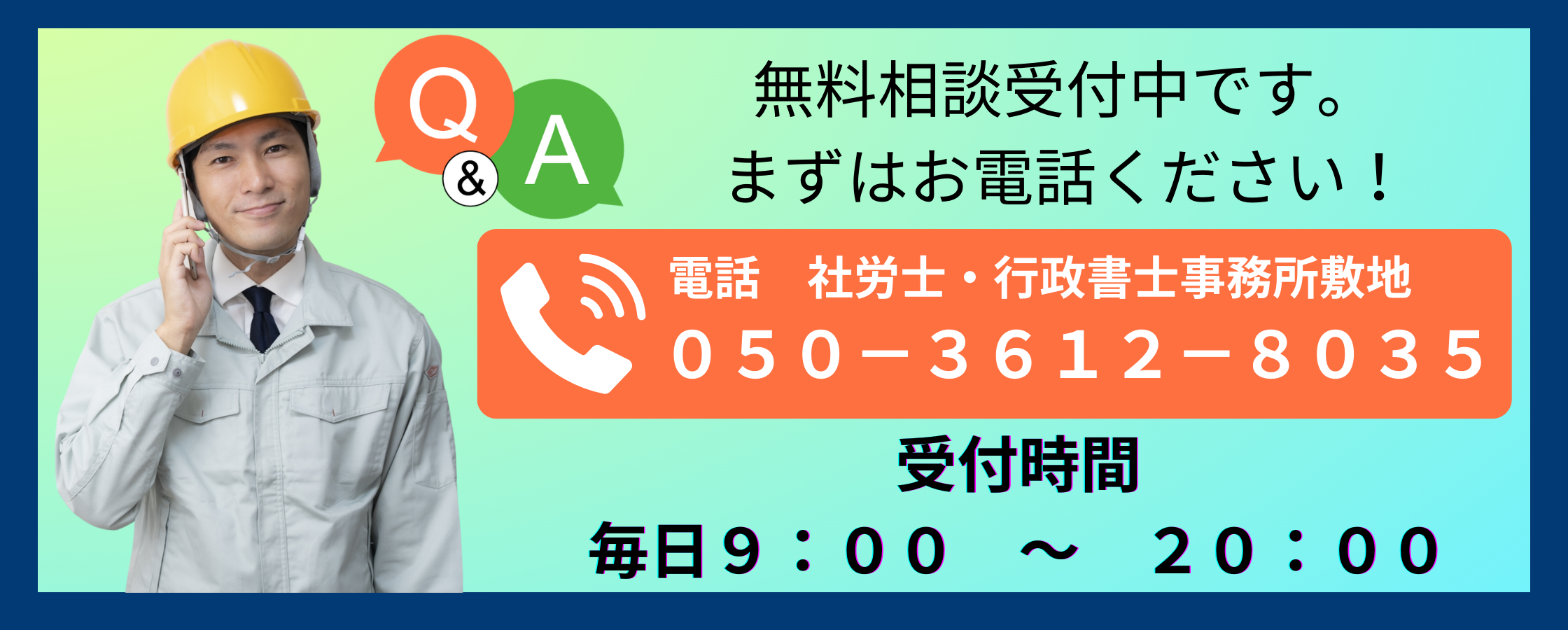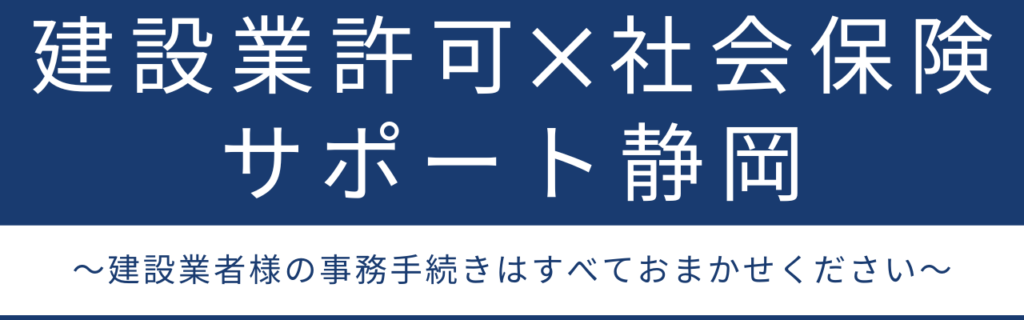建設業許可申請に関するよくある質問と回答のまとめ
静岡県において建設業許可の申請を進める際は、静岡県の「建設業の手引き」や「建設業許可事務ガイドライン」などの公式資料に沿って手続きを行うことが基本となります。
しかし実際には、「この場合はどうすればいいのか」「どこに確認すればよいのか」など、細かな点で疑問を抱く場面も少なくありません。
そうした場面で役立つよう、「よくある質問とその回答」を下記にまとめました。
建設業許可申請を進める際の参考として、ぜひお役立てください。
※記載内容は資料の改定等により変更される可能性があります。
正確な情報は、最新の「建設業の手引き」や静岡県の担当部署へご確認ください。
建設業許可申請に関するQ&A
- 建設業許可を取りたいのですが、相談に乗ってもらえますか?
-
はい、当事務所では「建設業許可の無料相談会」を実施しております。
申請をご検討中の方や、ご自身が許可を取得できるのか不安な方も、どうぞお気軽にご相談ください。現在、完全予約制にて個別に対応しております。
落ち着いた面談ルームで丁寧にヒアリングさせていただきます。あわせて読みたい 静岡の建設業許可申請の無料個別相談会を開催中|無料診断いたします。 静岡の建設業許可申請の個別相談会(無料)を静岡市駿河区の当事務所にて開催中|診断無料 ごあいさつ 当事務所のHPへお越し下さりありがとうございます。社労士・行政…
静岡の建設業許可申請の無料個別相談会を開催中|無料診断いたします。 静岡の建設業許可申請の個別相談会(無料)を静岡市駿河区の当事務所にて開催中|診断無料 ごあいさつ 当事務所のHPへお越し下さりありがとうございます。社労士・行政… - 敷地事務所では建設業者にどのようなことをしてくれるのですか?
-
建設業に関する手続き全般を、行政書士・社会保険労務士の立場から総合的に支援しています。
社労士・行政書士事務所敷地では、建設業許可の新規申請や更新、変更届、決算変更届、経審、入札参加申請などの許認可手続きをはじめ、社会保険・労働保険の加入手続き、労災特別加入、就業規則の整備等の相談など、建設業者が事業を行ううえで必要となる実務全般をサポートしています。
特に当事務所は、建設業界の実情をよく理解したうえで「許認可 × 労務」を横断的に支援できる体制を整えており、建設業に特化した事務所として静岡県内の事業者様を多数ご支援しています。
単発でのご依頼はもちろん、継続的にも「静岡の建設業手続パートナー」としての支援体制も整えていますので、お気軽にご相談ください。
あわせて読みたい 建設業許可✕社会保険サポート静岡の特徴|静岡市駿河区の社労士・行政書士敷地 静岡の建設業者様を社労士と行政書士がサポート|建設業許可(新規・更新)社会保険、労災、労務管理 当事務所のHPへお越し下さりありがとうございます。 私どもは静岡…
建設業許可✕社会保険サポート静岡の特徴|静岡市駿河区の社労士・行政書士敷地 静岡の建設業者様を社労士と行政書士がサポート|建設業許可(新規・更新)社会保険、労災、労務管理 当事務所のHPへお越し下さりありがとうございます。 私どもは静岡… - 建設業とは何ですか?
-
建設業法第2条第2項では、次のように定められています。
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業法第2条第2項つまり、建設工事を「完成させること」を請け負うビジネス全般が建設業に該当します。個人・法人を問わず、建設工事を受注して実施する場合には、原則として建設業許可が必要となる場合があります。
- 建設業の許可が必要な工事とは何ですか?
-
建設業法第3条第1項では、次のように定められています。
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法第3条第1項要約すると下記となります政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。
つまり、軽微な工事(一定金額以下の工事)だけを請け負う場合を除き、建設業を営むには許可が必要です。
- 建設工事とは何ですか?
-
根拠条文
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
建設業法第2条1項ここで言う別表第一の上欄に掲げるものとは、建設業29業種の事となります。
- 建設業の29業種とは何ですか?
-
建設業許可には、建設業法第2条および別表第一に基づき、次のように全29業種が定められています。
- 一式工事(2業種)
- 専門工事(27業種)
29業種の内訳は下記です。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
あわせて読みたい 建設業許可の業種29種類と内容 建設業許可業種の種類と内容についてご案内します。 このページでは建設業許可業種の種類とその内容についてお伝えをしていきます。建設業許可を取得しなければいけない…
建設業許可の業種29種類と内容 建設業許可業種の種類と内容についてご案内します。 このページでは建設業許可業種の種類とその内容についてお伝えをしていきます。建設業許可を取得しなければいけない… - 軽微な建設工事とは何ですか?
-
軽微な建設工事とは、次のいずれかに該当する小規模な工事をいいます。
【建築一式工事の場合】
該当は、土木一式工事と建築一式工事の2つのみです。
- 請負金額が1,500万円(税込)未満の工事
- または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
【建築一式工事以外の建設工事の場合】
該当は、上記の2業種を除く全27の業種です。
- 請負金額が500万円(税込)未満の工事
これらに該当しない工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
根拠法令
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
建設業法施行令第1条の2 - 附帯工事とは何ですか?
-
主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
建設業許可事務ガイドラインわかりやすく言うと:
メインの工事(例:建物の建築)を行うためにどうしても必要になる補助的な工事のことです。ただし、その附帯工事単体では用途を持たないものが該当します。
具体例:
- 建物の新築工事に伴って行う仮囲い工事や仮設足場の設置
- 地盤改良工事の前提としての整地作業
- 建物の建築に必要な仮設電気・水道の配管工事 等
- 請負契約とは何ですか?
-
請負契約とは、ある仕事の完成を約束し、その成果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法第632条わかりやすく言うと:
工事や製作物など、「成果物を完成させること」を条件に成立する契約であり、建設業では基本的な契約形態です。報酬は、作業そのものではなく、完成した成果に対して支払われるのが特徴です。
例:
- 建物を建てる工事契約
- 屋根の修繕を行う契約
- 道路舗装の工事契約 など
- 経営業務の管理責任者とは何ですか?
-
「経営業務の管理責任者」とは、建設業許可を取得するために必要な要件の一つであり、事業を適切に経営する能力を有する者として定められています。
(建設業法および国土交通省令による)国土交通省令で定める要件は次の2つです:
- 適切な経営能力を有していること
⇒ 建設業に関する一定期間の経営業務経験があること - 適切な社会保険に加入していること
これら両方を満たしていないと、「経営業務の管理責任者」として認められず、建設業許可を取得することができません。
詳しくは下記の記事にその内容をまとめていますのでご覧下さい。
あわせて読みたい 建設業許可の経営業務管理責任者についての解説 建設業許可の経営業務管理責任者について解説します。 建設業許可の許可基準 建設業の営業の禁止を解除するための建設業許可 建設業者は軽微な建設工事となるものを除き…
建設業許可の経営業務管理責任者についての解説 建設業許可の経営業務管理責任者について解説します。 建設業許可の許可基準 建設業の営業の禁止を解除するための建設業許可 建設業者は軽微な建設工事となるものを除き… - 適切な経営能力を有していること
- 経営業務の管理責任者としての経験とは何ですか?
-
建設業の「経営業務の管理責任者としての経験」とは、次のように定義されています。
法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
建設業許可事務ガイドラインわかりやすく言うと:
「経営業務の経験」とは、単に事務や現場を担当していたのではなく、会社や事業所の経営そのものに責任を持ち、売上・人員・契約などを総合的に管理していた経験が必要とされます。
また、「責任を有する地位」とは、名ばかりの役職ではなく、実質的に経営判断を行っていた立場であることが求められます。この地位は、登記簿に取締役として記載がされていることをもって証明することが一般的で、容易な方法となります。
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位とは何ですか?
-
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、次のように定義されています。
使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。
(昭和47年3月8日 建設省告示第351号)わかりやすく言うと:
- 法人の場合:専務や支店長など、会社の役員に次ぐ責任ある立場の人を指します
- 個人事業主の場合:事業主に次ぐ、現場責任者や経営判断に関与するような立場の人が該当します
これらの地位にある方が、実際に経営業務を管理していた経験がある場合は、経営業務の管理責任者と同等に扱われる可能性があります。
注意点
これらに該当することを自己申告や口頭で申し出ることでは受付けられず、実態として準ずる地位であることが書類で客観的に証明され、認められる必要があります。つまり、建設業許可申請においては証明が難しい部類のものとなります。 - 経営業務の管理責任者を補佐した経験とは何ですか?
-
経営業務の管理責任者を補佐した経験とは、次のように定義されています。
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいう。
建設業許可事務ガイドラインこちらも書類で証明する必要があり、それを示すことが難しい部類のものとなります。
- 経営業務の管理責任者は、他社の役員との兼務ができますか?
-
原則として、他社の非常勤役員との兼務は可能ですが、他社の「常勤役員」との兼務はできません。
建設業許可の要件にある「経営業務の管理責任者」は、申請者企業における常勤の役員でなければなりません。
この「常勤役員」について、ガイドラインでは以下のように定義されています。「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。
建設業許可事務ガイドラインわかりやすく言うと:
- 他の会社で非常勤役員(たまに会議に出る程度)をしている場合 → 兼務OK
- 他の会社で常勤役員(毎日出勤し、職務を行っている)をしている場合 → 兼務NG
建設業許可の審査においては、「本当にこの会社の経営をしているか」「毎日職務に従事しているか」が確認されるため、他社の常勤役職があると常勤性が疑われ、要件を満たさないと判断される可能性があります。
- 常勤性とはどのように確認するのですか?
-
常勤性は、健康保険証に記載された会社名であることをもって常勤しているものとみなされ、確認と証明がされてきました。しかし令和6年12月2日より健康保険証の新規発行は停止されたことに伴い、健康保険証で証明することが不可能となっていきますので、新たな常勤性の証明方法としていくつかの書類が採用されることになりました。
詳しくは下記の記事にその内容をまとめていますのでご覧下さい。
あわせて読みたい 建設業許可の常勤性証明の必要書類|経営業務の管理責任者、営業所技術者等 静岡の建設業許可における常勤性証明書類のご案内 常勤性証明書類ご説明の概要 この記事では経営業務の管理責任者と営業所技術者等がどのような書類を用意することで常…
建設業許可の常勤性証明の必要書類|経営業務の管理責任者、営業所技術者等 静岡の建設業許可における常勤性証明書類のご案内 常勤性証明書類ご説明の概要 この記事では経営業務の管理責任者と営業所技術者等がどのような書類を用意することで常… - 出向者を「経営業務の管理責任者」とすることはできますか?
-
結論としては可能ではありますが、それを書面で証明していくことが求められます。
具体的には下記のように示されています。
その者の勤務状況、報酬の支払状況、その者に対する人事権の状況等により常勤か否かの判断を行い、これらの判断基準により常勤性が認められる場合には、出向社員であっても経営業務の管理責任者として取り扱う。
これらの実態から「形式的な出向ではなく、実質的に出向先の企業の役員として常勤している」と認められた場合に限り、経営業務の管理責任者としての資格が認められます。
勤務表、報酬台帳、出向契約書などの書類を揃えていく事になりますが、まずは建設業許可の窓口へ相談をして対応をしていくことになります。
- 出向者を「営業所技術者等」として配置することはできますか?
-
はい、一定の条件を満たしていれば、出向者を営業所技術者等として認めることができます。
ただし、形式的な出向ではなく、実質的にその営業所に常勤して職務に従事している実態があることが前提です。それらを書類で証明をしていくことが求められます。
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人とは何ですか?
-
建設業法施行令第3条における「使用人」とは、次のように定義されています。
建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(本店を除く。)の代表者である者を指す。
建設業法施行令第3条わかりやすく言うと:
この「使用人」とは、単なる従業員ではなく、営業所などで建設工事の契約を締結したり、履行の指揮を行える責任ある立場の人のことです。
つまり、その営業所を代表し、実際に契約の責任を負うことができる地位にある者を意味します。
建設業許可申請をする際には、取締役と同じく公的書類の提出が必要となります。
- 営業所技術者等とは何ですか?
-
「営業所技術者等」とは、建設業許可を受けた事業者が各営業所に配置する、技術的な責任を担う常勤の職員のことです。
建設業法では、建設工事の契約や履行を適正に行うために、各営業所ごとにこの「営業所技術者等」を配置することが義務付けられています。建設工事に関する請負契約の適正な締結およびその履行を確保するため、各営業所ごとに、許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事について、常時その営業所に勤務している「営業所技術者等」を置くことが必要です。
建設業法施行規則・建設業許可事務ガイドライン※「専任技術者」という呼び名は「営業所技術者等」へ変更となりました。
- 営業所技術者等の資格とは何ですか?
-
「営業所技術者等」として建設業許可の要件を満たすためには、担当する建設業の種類に応じた資格または実務経験が必要です。
この資格要件は、建設業法第7条第2号および関連省令に基づき定められています。 - 営業所技術者等に求められる「実務経験」とは何ですか?
-
建設業許可において「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術的な職務に従事した経験のことを指します。
単なる補助作業や事務作業ではなく、技術上の職務として関わった経験でなければ認められません。
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。
建設業許可事務ガイドラインあわせて読みたい 静岡県知事建設業許可|営業所技術者の実務経験証明書について解説 静岡県知事建設業許可申請に必要な営業所技術者の実務経験証明書について解説 営業所技術者に必要な実務経験証明書のご案内 建設業許可申請を行う中で、営業所技術者を…
静岡県知事建設業許可|営業所技術者の実務経験証明書について解説 静岡県知事建設業許可申請に必要な営業所技術者の実務経験証明書について解説 営業所技術者に必要な実務経験証明書のご案内 建設業許可申請を行う中で、営業所技術者を… - 建設業における「専任の者」とは何ですか?
-
「専任の者」とは、ある営業所や工事現場において、常勤で勤務し、その職務だけに専念している者を指します。
建設業許可や各種手続において、特定の役割(例:営業所技術者等や主任技術者など)を担う際に求められる要件です。「専任の者」とは、その営業所に常勤して、専らその職務に従事することを要する者をいう。
建設業許可事務ガイドライン - 建設業許可における「請負契約に関する誠実性」とは何ですか?
-
建設業許可における「誠実性」とは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことを意味します。
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは令第3 条に規定する使用人が、個人である場合においてはその者又は令第3 条に規定する使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
建設業法第7条第3項 - 建設業許可で必要な「登記されていないことの証明書」とは何ですか?
-
「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人および被保佐人に該当していないことを示す、法務局が発行する登記事項証明書のことです。
あわせて読みたい 建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得代行 建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得代行を承ります。 登記されていないことの証明書とは 建設業許可申請を行う際には登記されていないこと…
建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得代行 建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得代行を承ります。 登記されていないことの証明書とは 建設業許可申請を行う際には登記されていないこと… - 建設業許可に必要な「身分証明書」とは何ですか?
-
「身分証明書」とは、建設業許可申請等の手続きにおいて、対象者が以下の法的制限に該当しないことを本籍地の市区町村が証明する公的文書です。
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
あわせて読みたい 建設業許可申請に必要な身分証明書について解説 建設業許可申請に必要な身分証明書について解説します。 身分証明書とは 一般的な身分証明書について 私どもが生活をしていく上で身分証明書の提示を求められるときは様…
建設業許可申請に必要な身分証明書について解説 建設業許可申請に必要な身分証明書について解説します。 身分証明書とは 一般的な身分証明書について 私どもが生活をしていく上で身分証明書の提示を求められるときは様… - 建設業許可に必要な「財産的基礎・金銭的信用」とは何ですか?
-
「財産的基礎・金銭的信用」とは、建設業を営むにあたって最低限必要な経済的な体力・信用があることを指します。
建設業法では、建設業者が安定して事業を遂行するために、一定の資金力や信用力を持っていることが許可要件とされています。許可を受けるにあたり、「請負契約を履行するための財産的基礎または金銭的信用」が必要とされています。
建設業法第7条第4号、建設業許可事務ガイドラインあわせて読みたい 建設業許可要件の財産的基礎500万円のご説明 この記事でご案内:建設業許可の財産的基礎500万円について 建設業許可5つの要件の1つに財産的基礎というものがあります。建設業許可申請をご検討された建設業者様…
建設業許可要件の財産的基礎500万円のご説明 この記事でご案内:建設業許可の財産的基礎500万円について 建設業許可5つの要件の1つに財産的基礎というものがあります。建設業許可申請をご検討された建設業者様… - 建設業許可に必要な「融資証明書」や「残高証明書」とは何ですか?
-
建設業許可申請では、500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。
そのための代表的な書類が「融資証明書」と「残高証明書」です。融資証明書
金融機関が、申請者に対し500万円以上の融資が可能であることを証明する書類です。
残高証明書
金融機関が、申請者名義の口座に500万円以上の残高があることを証明する書類です。
500 万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者であるか証明するためのものとして、担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500 万円以上の資金の融資を受けられる能力があるか証明するための書類
建設業許可事務ガイドライン - 建設業許可における「法定書類」とは何ですか?
-
「法定書類」とは、建設業法などの法令に基づき、許可申請時に必ず提出が求められる書類を指します。
提出先(都道府県・国土交通大臣)の違いにかかわらず、一律で必要とされる基本的な書類です。 - 建設業許可における「確認書類」とは何ですか?
-
「確認書類」とは、法定書類に記載された内容の正当性や裏付けを補足・確認するために、許可行政庁が申請者に対して提出を求める書類です。
法定書類は「提出必須」として法令で定められているのに対し、確認書類は自治体や審査官が内容を精査するために必要に応じて要求されるものです。
- 建設業許可の申請後に取り下げた場合、申請手数料は返金されますか?
-
いいえ、申請後に取り下げを行った場合でも、申請手数料は返金されません。
- 建設業許可を取得するための「許可の基準」とは何ですか?
-
建設業許可を取得するためには、建設業法に定められた5つの基準(要件)をすべて満たす必要があります。
- 建設業に関する経営経験(法第7条第1号)
- 技術者の設置(第2号)
- 誠実性(第3号)
- 財産的基礎(第4号)
- 欠格要件に該当していないことが必要である。(法第8条各号)
あわせて読みたい 建設業許可取得に必要な3つのポイントと5つの要件 静岡の建設業許可取得に必要な3つのポイントと5つの要件 このページでは、建設業許可取得に向けた考え方の概要についてお伝えしていきます。実際の許可申請では細かな…
建設業許可取得に必要な3つのポイントと5つの要件 静岡の建設業許可取得に必要な3つのポイントと5つの要件 このページでは、建設業許可取得に向けた考え方の概要についてお伝えしていきます。実際の許可申請では細かな… - 建設業の「知事許可」とはどのような場合に必要ですか?
-
建設業許可における「知事許可」とは、営業所の所在地が1つの都道府県内のみにある場合に必要となる許可です。
この場合、営業所が所在する都道府県の知事が許可行政庁となります。一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可行政庁となる。
建設業法第3条 - 建設業の「大臣許可」とはどのような場合に必要ですか?
-
大臣許可(国土交通大臣許可)は、複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする場合に必要です。
この場合の許可行政庁は、国土交通大臣になります。二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣が許可行政庁となる。
建設業法第3条 - 建設業許可の有効期間はどのくらいですか?
-
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可を受けた日から起算して5年が経過すると、その許可の効力は自動的に失効します。許可の有効期間は5年であり、許可の更新を受けなければその効力を失う。
建設業法3条第3項引続き建設業許可を有効とするためには建設業許可の更新が必要です。
あわせて読みたい 静岡県の建設業更新許可申請手続き代行 静岡県の建設業更新許可申請の手続き代行を承ります。 このページをご覧になられてる方は既に建設業許可を取得されている方だと思われます。建設業許可を取得後数年が経…
静岡県の建設業更新許可申請手続き代行 静岡県の建設業更新許可申請の手続き代行を承ります。 このページをご覧になられてる方は既に建設業許可を取得されている方だと思われます。建設業許可を取得後数年が経… - 電気工事業の建設業許可を取得しました。電気工事業登録は必要?どうしたらよいですか?
-
はい、建設業許可(電気工事業)とは別に「電気工事業登録」または「届出」が必要です。
これは、電気工事士法に基づく登録制度であり、
高圧・低圧問わず電気工事を請け負って施工する事業者は、原則として登録が義務です。あわせて読みたい 静岡の建設業者向け電気工事登録手続き代行 みなし登録電気工事業者届出手続き 当事務所のHPへお越し下さりましてありがとうございます。私は社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人と申します。このページで…
静岡の建設業者向け電気工事登録手続き代行 みなし登録電気工事業者届出手続き 当事務所のHPへお越し下さりましてありがとうございます。私は社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人と申します。このページで… - 建設業許可とは別に建築士事務所登録もしたいのですが、どうしたらよいですか?
-
建設業許可とは全く別の登録制度となります。建築士が所属して設計業務を行う場合には、建築士事務所としての登録が必要です。
詳しくは下記をご覧下さい。
あわせて読みたい 静岡の建築士事務所登録手続きを代行は当事務所へご相談ください 静岡の建築士事務所登録手続きを代行します。 社労士・行政書士事務所敷地のホームページへお越しくださりありがとうございます。このページでは建設業許可業者である法…
静岡の建築士事務所登録手続きを代行は当事務所へご相談ください 静岡の建築士事務所登録手続きを代行します。 社労士・行政書士事務所敷地のホームページへお越しくださりありがとうございます。このページでは建設業許可業者である法… - 建設業者として10人以上雇用することになりました。就業規則はどうしたらいいですか?
-
常時使用する労働者が10人以上になると、「就業規則の作成と労働基準監督署への届出」が法律上義務となります。
詳しくは下記をご覧下さい。
あわせて読みたい 建設業者のための就業規則をご提供します。 建設業許可に詳しい社労士が御社の就業規則を作成します。 当事務所のHPをご覧くださりありがとうございます。 私は事務所の代表者の成岡寛人と申します。行政書士と社…
建設業者のための就業規則をご提供します。 建設業許可に詳しい社労士が御社の就業規則を作成します。 当事務所のHPをご覧くださりありがとうございます。 私は事務所の代表者の成岡寛人と申します。行政書士と社… - 建設業者として労災の特別加入をしたいのですが、対応してくれますか?
-
はい、当事務所(社労士・行政書士事務所敷地)では、労災保険の特別加入申請をサポートしております。
建設業を営む中小企業の事業主、一人親方、法人役員の方が対象となります。詳しくは下記をご覧下さい。
あわせて読みたい 静岡の建設業者の労災特別加入(一人親方・中小事業主)お手続き 静岡の建設業者に必要な労災特別加入のお手続き 当事務所のHPへお越しくださりありがとうございます。 当事務所は建設業を営む事業主様をサポートすることに特化した…
静岡の建設業者の労災特別加入(一人親方・中小事業主)お手続き 静岡の建設業者に必要な労災特別加入のお手続き 当事務所のHPへお越しくださりありがとうございます。 当事務所は建設業を営む事業主様をサポートすることに特化した… - 建設業許可における「営業所」とは何ですか?
-
建設業法における「営業所」とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のいずれかに該当する場所をいいます。
- 建設業許可の変更届とはなんですか?
-
許可取得後に一定の情報が変わった際に、所定の期限内で届け出る必要がある手続きです。
建設業の許可を取得したあと、商号(社名)や代表者の変更、営業所の移転、経営業務管理責任者や営業所技術者の交代など、許可の内容に関わる情報に変更があった場合は、「変更届」を提出しなければならないと建設業法で定められています(法第11条・第12条ほか)。
この変更届を提出しないまま放置してしまうと、許可の更新ができなくなったり、経審の申請ができなくなったりする恐れがあります。最悪の場合、無許可状態とみなされ、行政処分の対象となることもあります。
特に、代表者や技術者、経営業務管理責任者の変更は2週間以内の届出が義務とされていますので、変更があった際はできるだけ早めに手続きを行いましょう。
あわせて読みたい 建設業許可変更届の種類と求められるとき 静岡の建設業許可 変更届の手続きと必要書類【提出期限も解説】 建設業許可の変更届の概要 建設業許可申請の際に記載した内容と、許可取得後の状況が変わる事はあるもの…
建設業許可変更届の種類と求められるとき 静岡の建設業許可 変更届の手続きと必要書類【提出期限も解説】 建設業許可の変更届の概要 建設業許可申請の際に記載した内容と、許可取得後の状況が変わる事はあるもの… - 営業所の商号が変わった場合、どのような手続きが必要ですか?
-
建設業許可においては、営業所の商号が変更された場合、「変更届」の提出が必要です。
あわせて読みたい 商号変更と建設業許可変更届の手続きと流れについて解説 商号変更と建設業許可変更届の手続きガイド 商号変更とは? 商号変更とは、社名変更のことです。商号変更を行うには、株主総会を開催して定款の変更決議を行い、商号変…
商号変更と建設業許可変更届の手続きと流れについて解説 商号変更と建設業許可変更届の手続きガイド 商号変更とは? 商号変更とは、社名変更のことです。商号変更を行うには、株主総会を開催して定款の変更決議を行い、商号変… - 営業所の名称(屋号など)が変わった場合はどうすればよいですか?
-
建設業許可においては、「変更届」を提出する必要があります。
あわせて読みたい 建設業許可後に営業所の名称変更を行うための手続きについて解説 建設業許可の営業所名称変更手続き|静岡県知事許可 建設業許可の営業所名称変更の概要 建設業許可における営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで…
建設業許可後に営業所の名称変更を行うための手続きについて解説 建設業許可の営業所名称変更手続き|静岡県知事許可 建設業許可の営業所名称変更の概要 建設業許可における営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで… - 営業所の所在地が変更になった場合はどうすればよいですか?
-
建設業許可においては、「変更届」の提出が必要です。
あわせて読みたい 建設業許可後に営業所の所在地変更を行うための手続きについて解説 建設業許可後の営業所の所在地変更届|静岡県知事許可 建設業許可の営業所所在地変更届の概要 建設業許可における営業所とは、原則として、本店、支店や常時建設工事の…
建設業許可後に営業所の所在地変更を行うための手続きについて解説 建設業許可後の営業所の所在地変更届|静岡県知事許可 建設業許可の営業所所在地変更届の概要 建設業許可における営業所とは、原則として、本店、支店や常時建設工事の… - 営業所の電話番号が変わった場合はどうすればよいですか?
-
建設業許可においては、「変更届」の提出が必要です。
あわせて読みたい 建設業許可後に営業所の電話番号変更を行うための手続きについて解説 建設業許可後の営業所電話番号変更の手続き|静岡の建設業許可 営業所電話番号変更届の概要 建設業許可では営業所の所在地と共に電話番号も届け出ています。 営業所に関…
建設業許可後に営業所の電話番号変更を行うための手続きについて解説 建設業許可後の営業所電話番号変更の手続き|静岡の建設業許可 営業所電話番号変更届の概要 建設業許可では営業所の所在地と共に電話番号も届け出ています。 営業所に関… - 一人親方の個人事業主ですが、建設業許可を取得するにはどうすればよいですか?
-
一人親方であっても、要件を満たせば建設業許可を取得することは可能です。
詳しくは下記の記事をご覧下さい。あわせて読みたい 静岡の建設業許可を個人事業主(一人親方)が取得する方法と必要書類 建設業許可、個人事業主でも取れます|まずは専門家にご相談ください 建設業を営む個人事業主(一人親方)の方へ 建設業を営む個人事業主(一人親方)の中には、より大…
静岡の建設業許可を個人事業主(一人親方)が取得する方法と必要書類 建設業許可、個人事業主でも取れます|まずは専門家にご相談ください 建設業を営む個人事業主(一人親方)の方へ 建設業を営む個人事業主(一人親方)の中には、より大… - 建設業許可の「決算変更届」とはどのようなものですか?
-
建設業者が毎事業年度終了後に提出する、決算内容を報告するための届出です。
正式名称は「変更届出書(決算報告)」であり、許可業者には毎年の決算終了後4ヶ月以内の提出が義務付けられています(建設業法第11条)。あわせて読みたい 建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)手続代行 静岡県の建設業許可決算変更届の手続き代行を承ります。 建設業許可の決算変更届とは 建設業許可の決算変更届とは、毎事業年度が終了した後の4ヶ月以内に届出をすること…
建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)手続代行 静岡県の建設業許可決算変更届の手続き代行を承ります。 建設業許可の決算変更届とは 建設業許可の決算変更届とは、毎事業年度が終了した後の4ヶ月以内に届出をすること… - 建設業許可に関する申請手数料はいくらですか?
-
静岡県で建設業許可を申請する際の手数料は以下の通りです。
いずれも「静岡県収入証紙」での納付が必要です。- 新規許可申請 9万円
- 更新許可申請 5万円
- 業種追加申請 5万円 等
- 静岡県知事許可に関する建設業許可申請の「標準処理期間」はどのくらいですか?
-
静岡県における建設業許可申請の標準処理期間は、受付後30日とされています。
ただし、これはあくまで書類が整って正式に受付された場合の目安であり、補正や5日以内の行政庁の休日の期間はカウントに含まれません。建設業許可申請の標準処理期間は、補正期間及び5日以内の行政庁の休日を除き、受付後30日。
静岡県許認可事項処理規定第2条及び第3条 - 建設業許可通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか?
-
いいえ、建設業許可通知書の再発行はできません。
〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉
建設業許可に関する
社会保険のQ&A
〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉