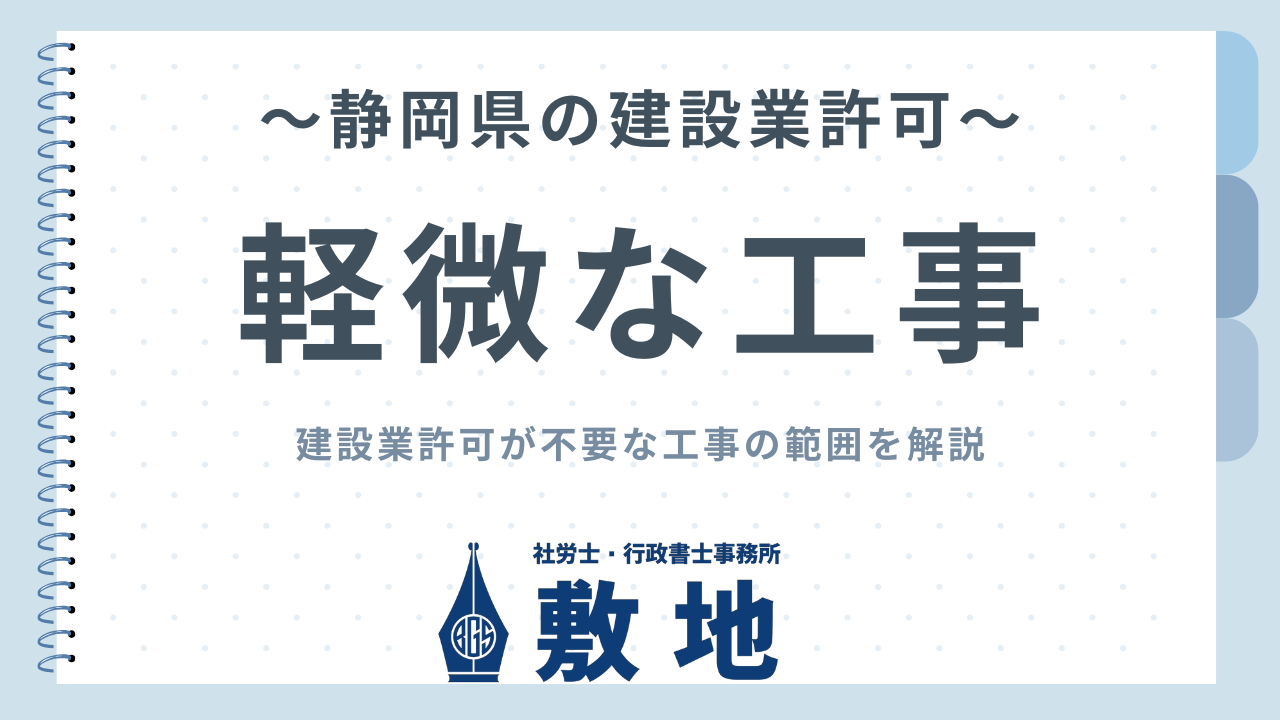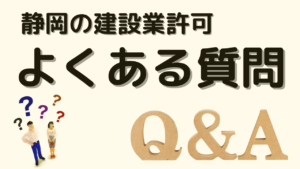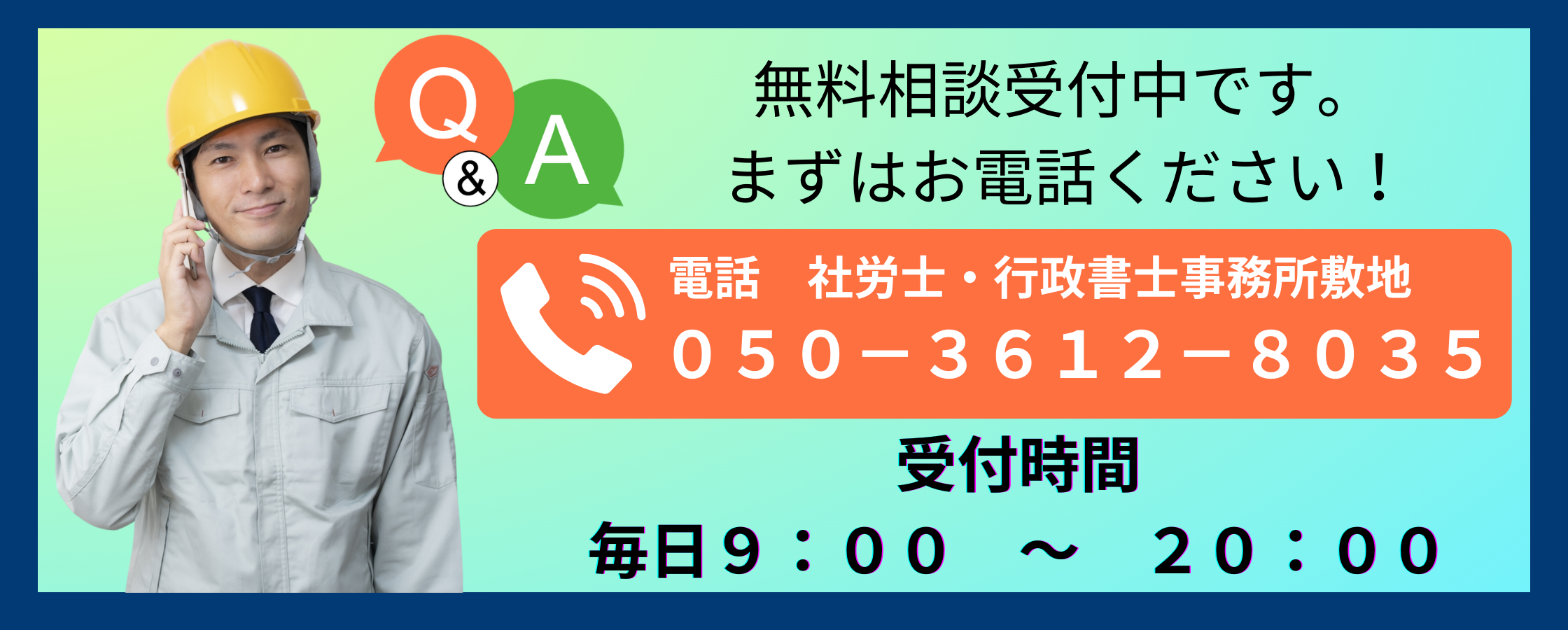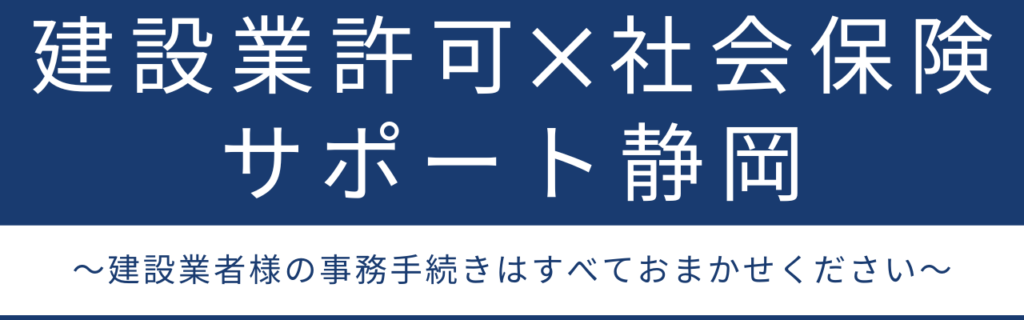建設業許可の軽微な工事について解説|静岡県の建設業許可
軽微な工事のみ請け負うなら、建設業許可は必要ないという話を聞いたことがあると思います。
具体的には、建築一式工事なら1,500万円未満、それ以外の建設工事なら500万円未満の場合です。
では、この請負金額を計算するにあたっては、どのように計算すればよいのか、消費税や材料費は含むのか?等について解説します。
このような方に向けた記事です
- 建設業許可が必要ない軽微な工事とは何かを知りたい方
- 軽微な建設工事の請負代金の額の計算方法を知りたい方
- 請負代金の額に消費税や材料費は含むのかを知りたい方
- 建設業許可を取得しないことのデメリットを知りたい方 等
建設業許可とは?
建設業を営む際は、営業所の所在地の都道府県知事から建設業許可を得なければなりません。
静岡県内であれば、静岡県知事から建設業許可を得るわけです。
静岡県の他、愛知県など他の都道府県にも営業所を設けている場合は、国土交通大臣の建設業許可が必要です。
建設業とは?
建設業の定義については、建設業法において下記のように定義されています。
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業法第2条2項(定義)
定義の内容をポイントに分けると下記のようになります。
| 用語の定義 | 事業の範囲 | 請負の種別 |
| 建設業 | 建設工事の完成を請け負う営業 | 元請 |
| 下請 | ||
| その他いかなる名義 |
建設工事とは?
そして、建設工事とは下記であるとされています。
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
建設業法第2条1項(定義)
別表第一の上欄と書かれておりますが、内容としては、土木一式工事、建築一式工事といった2つの一式工事と、大工工事、とび・土工・コンクリート工事などの27の専門工事のことを意味します。合計29の工事となります。
具体的には下記の業種です。
建設工事29業種の一覧表
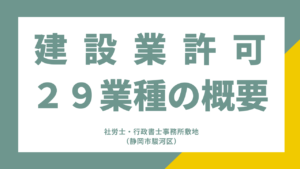
〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉
建設業許可が必要ない軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事については、建設業3条1項で下記であるとされています。
軽微な建設工事
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法第3条1項(建設業の許可)
では、「政令で定める軽微な建設工事」とは何でしょうか?
答えは、建設業法施行令1条の2に規定されています。
政令で定める軽微な建設工事
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
建設業法施行令第1条の2
この規定を読み解くと、軽微な建設工事に該当するのは次のような工事です。
軽微な工事に該当
次のいずれかに該当する工事
- 工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満の建設工事
- 延べ面積が、150㎡(45.38坪)未満の木造住宅工事
- 工事1件の請負代金の額が、500万円未満の建設工事
軽微な建設工事の請負代金の額の計算方法
軽微な建設工事に該当する請負代金の額は、建築一式工事で「1,500万円未満」、それ以外の建設工事で「500万円未満」となっています。この金額の計算方法については間違えやすいので注意しましょう。
年収や年間の売上高の事ではない
年収や年間の売上高が「1,500万円未満」または「500万円未満」であれば、建設業許可が必要ないと考えている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、建設業法で規定されているのは、「工事1件」あたりの請負代金の額のことです。
年収や年間の売上高ではありません。
同様に、月収やひと月の売上高の事でもありません。
一ヵ所の元請けからの請負代金の額の計算方法
一人親方や少人数の建設会社の場合、一ヵ所の元請けから専属的に建設工事の仕事を請け負っているケースも多いと思います。
この場合、一ヵ所の元請けから支払われる請負代金の合計額が、「1,500万円」または「500万円」以上になると、建設業許可が必要になると考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、こちらも認識としては間違いで、「工事1件」あたりの金額を意味します。
例えば、内装工事業者が、次の下請け工事を請け負ったとします。
一カ所の元請から請負
- A邸の内装工事を甲建設から300万円で請け負った。
- B邸の内装工事を甲建設から300万円で請け負った。
この場合は、A邸とB邸の内装工事は別の工事なので、どちらも軽微な工事に該当すると判断できます。
一ヵ所の工事現場の請負代金の額の計算方法
一ヵ所の工事現場の工事について、一期、二期と分けて建設工事を請け負う場合もあります。
この場合は、原則として、すべての工事の合計額が「1,500万円」または「500万円」以上かどうかで判断します。
建設業法施行令では下記のように示されています。
前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
建設業法施行令第1条の2、2項(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
例えば、内装工事業者が、次の下請け工事を請け負ったとします。
- Aマンションの第一期内装工事を甲建設から300万円で請け負った。
- Aマンションの第二期内装工事を甲建設から300万円で請け負った。
この場合は、第一期と第二期の内装工事を合算すると、600万円になるので、軽微な工事とは言えず、建設業許可が必要になります。
〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉
消費税は請負代金の額に含まれるのか?
請負代金の額には、消費税を含むのでしょうか?
答えは、含みます。
より具体的には、「消費税」及び「地方消費税相当額」を含んだ金額が「税込」となり、これを請負代金の額に含まれます。
※1「請負代金の額」とは、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額(以下「税込み」という。)をいいます。
静岡県の建設業許可の手引きより
例えば、内装工事業者が税抜き価格490万円で内装工事を請け負った場合は、税込み価格で539万円になるので、軽微な工事とは言えず、建設業許可が必要になります。
表に当てはめると下記のようになり、軽微な工事とならないことがわかるかと思います。
| 項目 | 金額 | 請負代金合計 | 建設業許可の要否 |
| 請負代金 | 490万円 | 539万円 | ・建設業許可必要 ・軽微な工事に該当しない |
| 消費税等 | 49万円 |
材料費は請負代金の額に含まれるのか?
建設工事では、建材などの材料が必要になりますが、材料を誰が支給するのかにより、請負人が受け取る金額が異なります。
請負人が材料も用意する場合は、材料の価額と一緒に注文者側に請求することになります。
この場合の「1,500万円」または「500万円」の判断は、材料や運送賃の価額も含めた金額で行います。
例えば、内装工事業者が、代金として600万円を注文者に請求したとします。
その内訳のうち、材料や運送賃の価額が200万円だったとします。
| 項目内訳 | 金額内訳 | 請負代金合計 | 建設業許可の要否 |
| 請負代金 | 400万円 | 600万円 | ・必要 ・軽微な工事に該当しない |
| 材料+運送費 | 200万円 |
この場合、材料や運送賃を差し引けば、実際の請負代金の額は400万円と考えるかもしれませんが、そうではなく、請求した金額全体で考えます。
そのため、請負代金の額は600万円になるので、軽微な工事とは言えず、建設業許可が必要になります。
注文者側が材料や運送賃を負担している場合でも同じです。
この場合、内装工事業者が実際に請求する請負代金の額は400万円ですが、軽微な工事に該当するかどうかの判断では、材料や運送賃の額も含めて計算します。
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
建設業法施行令第1条の2、3項(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
そのため、請負代金として400万円しか受け取っていなくても、軽微な工事とは言えず、建設業許可が必要になります。
| 項目 | 金額 | 請負代金合計 | 建設業許可の要否 |
| 請負代金 | 400万円 | 実質600万円 | ・必要 ・軽微な工事に該当しない |
| 材料+運送費 (注文者が負担) | 請求無し (実質:200万円) |
〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉
より大きな請負に備えて建設業許可を取得
建設業許可がないと、大きな工事の依頼が舞い込んだ時に断らなければなず、ビジネスチャンスを逃してしまうことがあります。
建設業許可の申請は、間違いの無いすべての申請書類と添付書類が揃っていたとしても、どれだけ早くても1ヶ月以上の時間が必要です。具体的には下記のように時間が必要です。
| 工程 | 期間(ご自身で行う場合) | 期間合計 |
| ① 許可可能性の確認 | 1ヶ月~? | 4ヶ月~ |
| ② 申請書類の準備 | 2ヶ月~? | |
| ③ 申請~許可 | 約1ヶ月 |
※建設業専門の行政書士へ依頼すると①、②の期間が大幅に短縮されます。
上記のように、建設業許可はすぐに取得ができるものではありませんので、軽微な工事に該当するか微妙な請負代金額の工事が続くときは、早めに建設業許可を取得しておきましょう。
また、一般の依頼者が家の修理をしてくれる業者を探すときも、建設業許可を取得しているかどうかで判断していることがあります。
そのため、軽微な工事の仕事しか来ない場合でも、早めに建設業許可を取得しておく方が望ましいでしょう。
その他、附帯工事という考え方もあるのでこちらも押さえておきましょう。
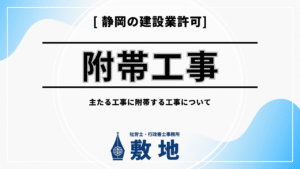
まとめ
軽微な工事のみ請け負う場合は、建設業許可は必要ありません。
ただ、建設業許可がないと、大きな仕事が舞い込んだ時に断らなければならなかったりして、ビジネスチャンスを逃してしまうこともあります。
こうした事態を避けるためにも、できるだけ早めに建設業許可を取得しておきましょう。
当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得に関してお悩みのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。