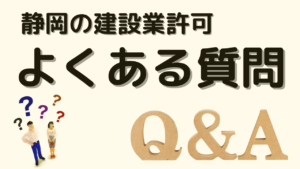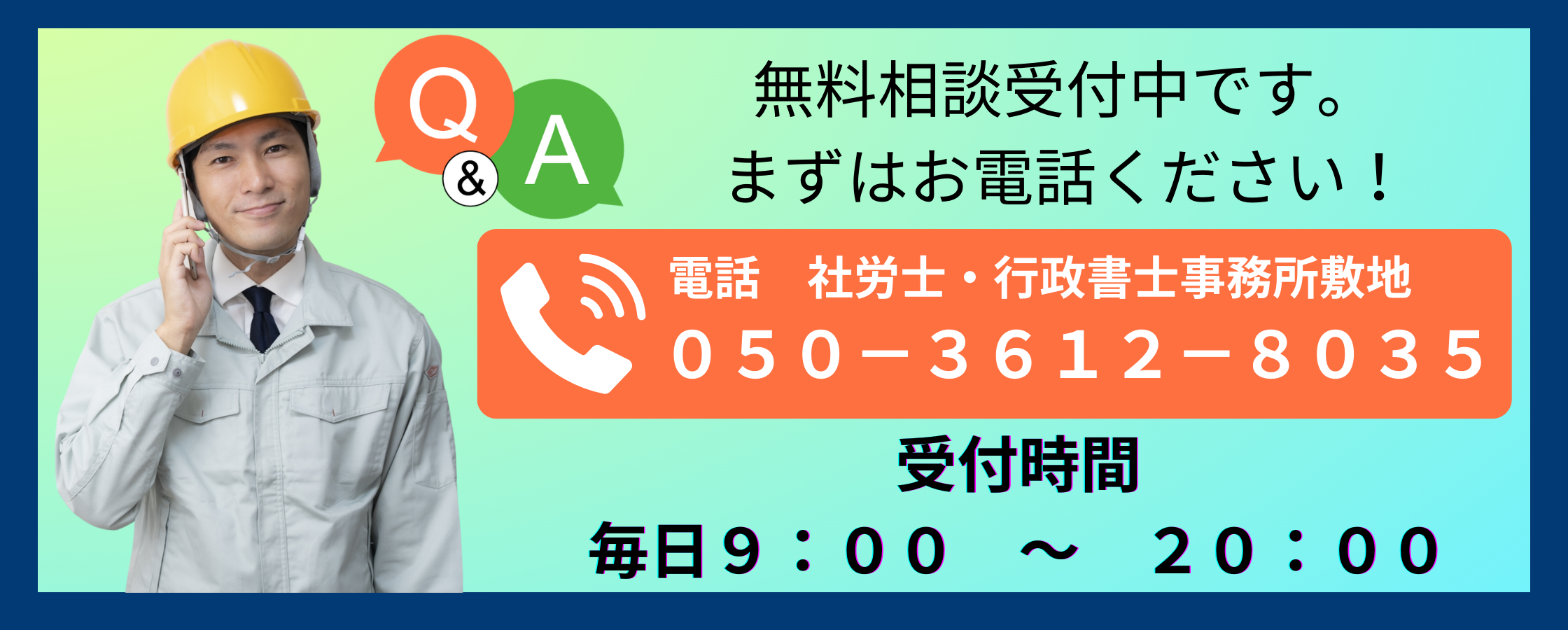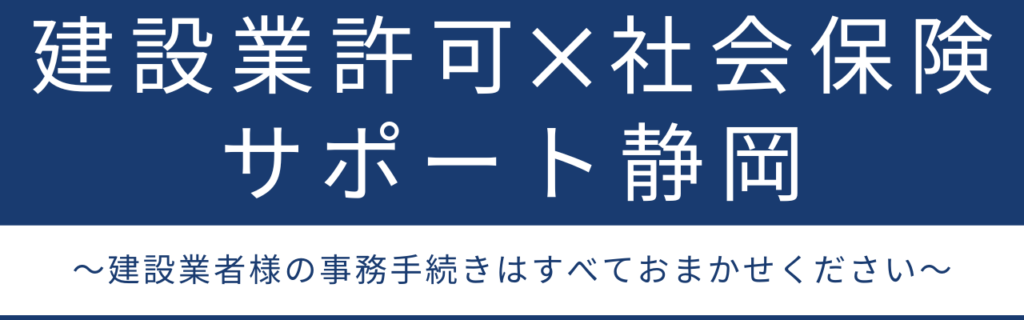建設業許可についての概要ご説明
建設業者様のさまざまなご事情において、建設業許可取得のご検討をどこかのタイミングで始められることがあるかと思います。これまでの建設業者としての活動と比べて何が違い、何ができるようになるのか。また、そのようなルールとなっているのか。この記事ではそのあたりの概要をご説明いたします。
このような方のお役に立つ内容となっています。
- 建設業許可がどのようなものなのか知りたい方
- 建設業許可の制度について知りたい方
- 請負代金のルールについて知りたい方
建設業許可の制度とはどのようなものなのか
建設業許可とは、建設業法をはじめとした各種の法令等で定められ、これらで求められた要件をクリアすることにより建設業許可が取得できる。という事を定めた制度になります。
しかし法律の条文を一つ一つ読み込んで要件を確認していく事はとても大変な作業となりますため、まずは建設業許可とはどのようなものなのか、概要をこの記事でご確認いただけたらおおよそ求められることをご理解いただけるものと思います。ぜひ最後までご覧ください。
建設業許可を取得ができる業者
建設業許可はどのような業者が取得することができるのでしょうか?
建設業を営む場合には、法人、個人、元請、下請と言った区分に関わらず建設業許可を取得することができます。また、一定の条件を超える場合には建設業許可の取得が義務付けられます。
上記の内容を下記の表へ置き換えてご案内します。
| 事業の形態 | 元請、下請けの別 | 建設業許可 |
| 法人 | 元請 | 取得可 |
| 下請 | ||
| 個人 | 元請 | |
| 下請 |
建設業許可を取得しなければならない場合
建設工事の完成を請負う事を営業とするには、建設工事の種類に対応した業種ごとに建設業の許可を取得しなければならないこととされています。但し、軽微な建設工事(小規模な建設工事)のみを請負う場合には取得は義務ではありません。
基本的には建設業許可を取得が必要
軽微な建設工事とは?
下記にあたる工事は「軽微な建設工事」とされていて、建設業許可を取得していることを求められません。
下記のいずれかに該当する建設工事
① 工事1件の請負代金の額が、1500万円未満の建設工事
② 延べ面積が150㎡(45.38坪)未満の木造住宅工事
用語の説明
- 延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計となります。
- 木造とは、建築基準法で定める主要構造部が木造であるものをいいます。
- 住宅とは、住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住用に使用するものをいいます。
工事1件の請負代金額が500万円未満の建設工事
補足説明
- 上記2点の請負代金の額とは、消費税等を含んだ税込金額の事となります。
- 注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合には、その市場価格と運送費を加えた金額とすることとされています。
請負代金とは税込金額のこと
材料支給の場合には市場価格と運送費が請負代金に加算される
請負代金の計算の例(建築一式工事以外の場合)
| 項目 | 金額(税込) | 工事費合計金額(税込) |
| 請負契約代金 | 420万円 | 520万円 |
| 支給材料費 | 100万円 |
この場合、請負金額は税込500万円未満ですが注文者からの支給材料費が100万円あり、これを合計すると税込520万円となるため、建設業許可が必要な建設工事となります。
軽微な工事のまとめ表
| 求められる項目 | 建築一式工事以外 | 建築一式工事 |
| 1件の請負代金 | 500万円未満 | 1500万円未満 |
| 木造住宅工事での延べ床面積 | ー | 150m2未満 |
建設業許可が必要な工事のまとめ表
| 求められる項目 | 建築一式工事以外 | 建築一式工事 |
| 1件の請負代金 | 500万円以上 | 1500万円以上 |
| 木造住宅工事での延べ床面積 | ー | 150m2以上 |
建築一式工事の場合はどちらかが該当したら建設業許可取得が必要です。
建設業許可の区分
建設業許可は、一般建設業の許可と特定建設業の許可の2種類があります。
一般建設業許可は建設業者がまず初めに取得することが多く、元請け、下請けを問わず多くの建設業許可業者が取得しているものとなります。一方で、特定建設業許可は下請負人を保護するために設けられた元請業者に対しての制度で、下請けに対して出す金額が一定を超える場合には取得することが求められます。
一般建設業許可と特定建設業許可の区分の詳細
発注者から直接請け負う1件の建設工事にうちて、その工事の全部又は一部を下請代金の額が税込4500万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要な許可
ポイント
※1 建築一式工事の場合は、税込7000万円以上と読み替える
※2 下請契約が2以上ある場合は、その合計額
※3 消費税を含む
※4 元請負人が提供する材料等の価格は含まない

元請であることと、4500万円以上かが
最初のポイントだね。



はい。おっしゃるとおりです。
下請への金額が合計される事にも注意が必要ですね。
特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可



特定建設業以外の場合が
一般建設業なのね。



はい。そのようになります。
4500万円未満なら一般建設業許可ですね。



下請の受注金額には上限は無いという事で
よいのかね?



はい。あくまでも元請についての制度ですので
下請として請け負う金額に上限はありません。
| 業者の位置づけ | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
| 元請 | 取得可 | 4500万円以上の場合取得 ※建築一式は7000万円以上 |
| 下請 | 取得可 | 下請は不要 |
大臣許可と知事許可
建設業許可は営業所の所在地により国交省大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)の2つに分かれます。
大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を持って営業する場合に必要な許可です。それに対して、知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を持って営業する場合に取得する許可です。
| 許可の種類 | 1つの都道府県内にのみ営業所 | 2つ以上の都道府県内に営業所 |
| 知事許可 | 〇 | ー |
| 大臣許可 | ー | 〇 |
ここでいう営業所とは、常時建設工事に関する見積、入札、請負契約等の実体的な業務を行う事務所のことで、工事事務所や連絡所などは営業所にはあたりません。
| 常時建設工事に関する | 建設業許可上の営業所 | |
| 見積 | 該当 | |
| 入札 | 該当 | |
| 請負契約 | 該当 | |
| 工事事務所 | 非該当 | |
| 連絡所 | 非該当 | |
| 置き場 | 非該当 | |
業種別建設業許可29業種
建設業の許可は、建設工事の種類で区分された業種ごとに許可を受ける必要があります。
全部で29の許可業種があり、2つの一式工事と27の専門工事に分かれています。詳しくは下記の記事でまとめていますのでご覧ください。
建設業許可の基準
建設業法は軽微な建設工事を除き、許可を受けずに建設工事を営業することを禁止しています。この営業の禁止を解除して営業できるために5つの要件を定めています。
- 経営業務の管理を適正に行う能力があること(経営業務の管理責任者)
- 営業所に専任の技術者がいること(専任技術者)
- 請負契約に関して誠実性があること(誠実性)
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること(財産要件)
- 欠格要件等に該当しないこと(欠格要件)
建設業許可を取得するためにはこれらの要件をクリアする必要があります。その具体的な内容については下記の記事に書いていますのでよろしければご参照ください。
建設業許可の概要まとめ
いかがでしたでしょうか。建設業許可の概要についてのご理解が進みましたでしょうか。
建設業許可の区分では一般建設業許可と特定建設業許可がありました。また、営業所が都道府県内に1つなのか、又は2つ以上の都道府県にまたがるのかにより知事許可と大臣許可に分かれました。そのほか、軽微な建設工事のみの場合には建設業許可は取得する必要はありませんが、税込500万円以上となる工事を請ける場合には建設業許可を取得しなければならないことがおわかりいただけたかと思います。
まずはこの概要を理解し、どのタイプの許可が必要なのかをお選びいただくことから始まります。一般的には一般・知事許可の取得から始められることが多いです。
ご不明点はまだおありの事と思いますが、当事務所では無料相談も承っておりますため、疑問点についてはお問合せ頂けましたら幸いです。